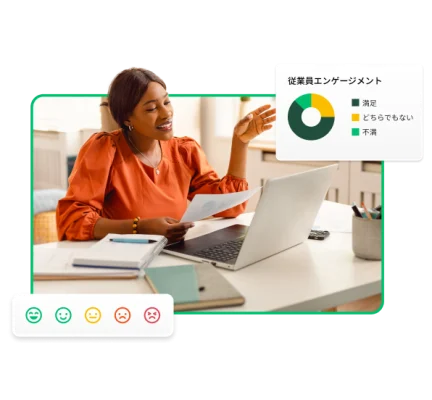
離職率は、特定の期間に退職する従業員の割合を示します。離職率が高い企業では、従業員の満足度が低い、労働条件が悪い、従業員の意欲が低いなどの特徴が見られます。
この記事では、離職率の計算方法について説明するだけでなく、ベンチマーク比較をして離職率の改善に生かし、全体的な従業員体験を向上させる方法もご紹介します。
離職率とは
先ほどもご説明したとおり、離職率は、一定の期間内に退職する従業員の割合を示す指標です。
離職率が低い企業は、従業員の満足度が高い傾向にあり、生産性やエンゲージメント、収益も総じて高くなります。離職率が下がることで職場が変わり、働きやすい職場文化が醸成されます。
離職率を計算する3つのステップ
離職率は、計算式を使って最終的な割合を計算できます。
こちらが離職率の計算式です。
- 離職率 = (退職した従業員数 ÷ 平均従業員数)× 100
離職率はこの計算式(または離職率計算ツール)を使って、退職した従業員数を平均従業員数で割った値に100を掛けて導きます。
詳しくは、以下の3ステップで計算します。
- 平均従業員数を計算する: 年度初めの従業員数と年度末の従業員数を足します。その数を2で割ります。
- 退職した従業員数を計算する: 年度中に何人の従業員が退職したかを出します。
- 計算式を使用する: ステップ1と2で出した数字を式に当てはめ、割ります。その数に100を掛けると、離職率を割合で示すことができます。
例として、年度初めに200人の従業員が在籍しており、年度末には300人に増えた会社の離職率を出してみましょう。年間の平均従業員数は、(200+300)÷2=250 を計算して、250人になります。この年に10人の従業員が退職していれば、年間離職率の計算は 10÷250x100=4 となり、4%ということがわかります。
離職率の分析方法
離職率は計算して終わりではなく、さらに分析を行うことで、従業員体験に関する企業の取り組みが功を奏しているかどうかを確認できます。離職率が一般的な値より高ければ、EVP(従業員の価値提案)や全体的な従業員体験を改善する必要があります。
計算した離職率を常に業界全体や自社の過去のデータとベンチマーク比較して、立ち位置を把握しましょう。同業他社と比較することで、今の方針が正しいかどうかがわかります。その上で、自社の過去の離職率と年単位で比較すると、職場環境が改善しているのか、それとも悪化しているのかが明らかになります。
ベンチマーキングは、従業員体験を継続的に改善しながら離職率を下げようとする企業にとって重要な戦略です。
ここで、離職には自発的離職と非自発的離職の2種類あることを押さえておいてください。
自発的離職と非自発的離職
従業員が離職に至る理由はさまざまです。理由は大きく2つの種類に分けられ、それぞれが意味することは異なります。
- 自発的離職: 従業員に選択肢があり、自ら会社を辞めることを選択した場合は、自発的離職となります。転職や引退など、さまざまな理由があります。
- 非自発的離職: 従業員に選択肢がなく、自らの意思に反して会社を辞める場合は、非自発的離職となります。会社が一部の従業員を一時解雇したり、特定の従業員をリストラしたりする場合が該当します。
離職率にはどちらの種類も含まれますが、全体像を掴むために、それぞれの離職率を個別に計算することをお勧めします。
平均的な離職率は?
2024年の米国の月間平均離職率は、全業界で2.1%でした。このデータは労働統計局の調査結果から得たもので、過去数年と比べて著しく低い数値です。
ただし、これは全体の平均ですので、小売などの一部の業界は他よりも高いことを忘れてはいけません。業界別の年間平均離職率は以下のとおりです。
- 採掘・伐採: 5.9%
- 建設: 4.6%
- 製造: 4.6%
- 金融サービス: 5%
- 娯楽・ホスピタリティ: 7.2%
- 飲食: 4.3%
- 政府機関: 4.3%
- 医療・社会支援: 7.5%
- 専門的・事業向けサービス: 6.7%
離職率の平均値や相対的な高さを調べる場合は、必ず該当する業界のベンチマークを探してください。
高い離職率とは
高い離職率とは、業界の平均離職率よりも高い数値を意味します。たとえば、先ほどの業界別平均値を基にして、ある医療機関の離職率が高いと言う場合は、年間7.5%を超えていることになります。
離職率が高いか低いかを確認するときには、常に最新のデータをご利用ください。
低い離職率とは
低い離職率とは、業界の平均離職率よりも低い数値を意味します。たとえば、サービス業(ホスピタリティ)では年間7.2%に満たない場合に離職率が低いと言えます。これが4%ともなれば、業界的に極めて低い数値です。
以上の作業を経て離職率が高いことが判明した場合は、下げるための戦略を練り、対策を講じましょう。
高い離職率の原因は?
従業員がたった1つの理由で会社を辞めることはほとんどありません。
大抵、次のようなさまざまな問題が積み重なった末に辞めたくなるものです。
- 仕事での成長やキャリア開発ができない
- リモートワークやハイブリッドワークができない
- 従業員エンゲージメントが低い
- 通常の昇進
- 社内の昇進や異動
- 従業員の燃え尽き症候群
- 経営陣に対する負の感情
- ストレスの多い職場環境
- 家族・ライフイベント
- 条件の良い他社に転職
- ワークライフバランスの問題
- 非自主的な退職(レイオフ、解雇など)
このような離職率に影響を与えている要因は、退職アンケートや従業員のモニタリングを実施することで特定しやすくなります。
離職率を下げる方法: 6つのヒント
離職率を下げるために役立つ従業員の定着戦略を6つにまとめてご紹介します。
1. 離職率を継続的に追跡する
離職率をベンチマーク比較し、毎月の推移を継続的に測ることで、従業員体験の戦略が成果を上げているかどうかを判断できます。
定期的な測定をしていなければ、長期的な変化を知るための基準となるデータがありません。離職率はぜひ、主要な従業員体験KPIの一つに位置付けてください。
離職率に関するデータが集まれば集まるほど、離職率を下げるために効果的な戦略を立てることができます。
2. 従業員定着の6つの柱に焦点を当てて離職率を下げる
従業員が定着するかどうかには複数の要因が関係しています。これらはすべて、会社が従業員のライフサイクルを通じて提供する体験全般に深く関わっています。
従業員定着の6つの柱と離職率との関係を簡単にご説明します。
- 職場環境: 共同作業を促進し、プライバシーを守り、効率的に仕事を進めるために必要なものをすべて備えた職場環境を設計しましょう。
- エンプロイヤーブランディング: 他社にはない魅力的な価値を従業員に提案することで、人材を惹きつけることができます。評判が高まれば、人は自ずと集まります。
- 企業文化: 公平で、互いを尊重し、インクルージョンを促進する企業文化でこそ、従業員は生き生きと力を発揮できます。
- 従業員の表彰: 日頃の従業員の貢献に対して感謝を示す場として、従業員の表彰が効果的です。努力を評価して報いることで、さらに意欲を高め、長く働き続けたいという気持ちを引き出せます。
- 能力開発とキャリアの機会: 明確な能力開発のチャンスがないと、従業員はステップアップする場を他に求める可能性があります。
- 従業員の健康とウェルビーイング: ウェルビーイングと精神衛生のプログラムに投資すると、従業員の燃え尽き症候群を減らし、サポートができます。健康的な従業員は、高い満足度につながります。
従業員エンゲージメントの行動計画を作成するには、まず、定着の柱を理解し、それぞれに取り組むことから始めましょう。
関連トピック: 人事のクイック スタート ガイド
3. 従業員の表彰プログラムに投資する
表彰をすると、従業員の日頃の努力と貢献に感謝していることを伝えることができます。SurveyMonkeyの調査によると、表彰された従業員の63%が、6ヶ月以内に転職を模索する可能性が低いことを示しています。従業員表彰プログラムを立ち上げることは、従業員パフォーマンスの全体像を把握するための1つの戦略となります。
表彰プログラムには、フィードバック文化の一環として従業員の仕事を讃える役割もあります。長期的な視点で、従業員を表彰して感謝の意を示すことで、燃え尽き症候群を減らし、生産性を高め、離職率を下げることができます。
4. 従業員フィードバック文化を醸成する
従業員フィードバックは、チームの意欲を高め、従業員体験を向上させる最も効果的な方法の一つです。
従業員ライフサイクルの各段階で従業員エンゲージメントアンケートを実施することもできます。フィードバックを収集し、従業員がその時点で感じていることをより深く理解しましょう。改善の必要な従業員体験の領域を示してくれるでしょう。
従業員フィードバックは、人事評価、1対1の面談、フィードバックアンケートなどで収集できます。
従業員ライフサイクルの段階ごとに、次のような効果的な従業員体験アンケートを利用できます。
採用
採用段階の従業員フィードバックを収集するのに最適なアンケートが、候補者体験アンケートです。このアンケートテンプレートを使うと、採用がどのように行われているかを候補者の視点から確認できます。
候補者体験アンケートではリッカート尺度を使用して、採用プロセスに対する満足度を測定します。
オンボーディング
採用後のオンボーディング期間中にフィードバックを収集するための従業員体験アンケートは4つあります。
- 新入社員オンボーディングアンケート: 新入社員オンボーディングアンケートでは、職場やトレーニングの効果を評価します。
- 30日間オンボーディングアンケート: 30日間オンボーディングアンケートでは、新規採用者にチームから歓迎されたと感じるか、最初の1ヶ月間がどうだったかを尋ねます。
- 60日間オンボーディングアンケート: 60日間オンボーディングアンケートでは、従業員が自分の役割を理解しているかを確認できます。また、従業員の成長を支援する方法を把握することも可能です。
- 90日間オンボーディングアンケート: 90日間オンボーディングアンケートでは、従業員が追加の指示を必要としているかどうかを判断できます。
各アンケートで、オンボーディングプロセスの効果を測定し、従業員がサポートを必要としているかどうかを知ることができます。最善のスタートを切り、離職率の低下につなげましょう。
能力開発
従業員ライフサイクルの能力開発段階は、従業員が各自の役割に慣れてきた段階です。もっと責任を負い、組織内での影響力を高める機会を求める従業員が増えてきます。
能力開発段階での満足度を測定し、離職率を下げるのに役立つ従業員フィードバックアンケートを3つご紹介します。
- 職業能力開発アンケート: 職業能力開発アンケートでは、従業員が希望している能力開発の道筋を把握します。能力開発を求める理由を尋ねることで、潜在的な昇進のルートを具体的に掴むことができるでしょう。
- 人事評価アンケート: 人事評価アンケートでは、従業員の進捗状況と生産性をモニタリングします。このアンケートを使って、チームへの影響について尋ね、強みや改善すべき点を特定しましょう。
- キャリア開発アンケート: キャリア開発アンケートでは、従業員エンゲージメントをモニタリングし、トレーニング内容を改善すべき分野を把握します。
SurveyMonkeyの調査では、社内でのキャリアアップの機会が非常に充実していると評価している従業員は、わずか27%でした。上記のアンケートを活用することで、教育を重視する組織へと優先的に取り組むことができます。
関連トピック: 従業員エンゲージメントの結果を収集・共有するためのベストツール
維持
従業員ライフサイクルの中での維持段階は、ベテラン社員からフィードバックを集めるチャンスです。
以下のアンケートを使って従業員の満足度を明らかにし、従業員体験をさらに洗練する機会を探しましょう。
- 従業員福利厚生アンケート: 従業員福利厚生アンケートは、会社が提供している福利厚生が従業員の期待に沿っているかどうかを確認します。この結果に従って、さらに充実した従業員価値提案をすることができます。
- ワークライフ バランス アンケート:ワークライフ バランス アンケートは、従業員が現在のワークライフバランスを持続可能だと思っているかどうかを調査します。満足度を尋ねる質問で、従業員の燃え尽き症候群を防止・軽減しましょう。
- ワーク エンゲージメント アンケート: ワーク エンゲージメント アンケートは、従業員に最大限の努力をする意欲があるかどうかを確認するアンケートです。また、仕事についてどう感じているかも把握でき、エンゲージメントの低い従業員を見つけて対策を打つきっかけになります。
- 報酬・福利厚生アンケート: 競争力のある報酬は、どのような職種でも重要です。報酬・福利厚生アンケートでは、医療保険や有給休暇、退職金に対する満足度など、改善点を見つけることができます。
従業員フィードバックを導入して定着率を高め、離職を減らし、職場の満足度を高めましょう。
退職
効果的な退職アンケートの力は侮れません。従業員が退職する際には、ぜひ退職面談の糸口に活用してみてください。
退職面談では、退職する理由を明らかにします。離職の背景にある重大な理由をピンポイントで把握しなければ、対処するための戦略を練ることはできません。
回を重ねるごとに、退職面談を貴重な従業員フィードバックを得る場としてうまく活用できるようになるでしょう。見送ることは残念ですが、その経験をうまく生かせば、最終的に労働条件の改善につながります。
これと併せて、離職に至る前の従業員にステイインタビューも実施すると、ニーズをより詳細に追跡できます。
5. 能力開発を強化して離職率を下げる
高い離職率の主な要因の1つは、従業員が今の仕事に行き詰まりを感じていることです。学びや成長の機会がないと、社内で昇進する展望が見えないと感じるかもしれません。
従業員トレーニングの教材やコース、自習モジュールなどに投資して、従業員が成長する能力開発の機会を提供しましょう。以下のような方法があります。
- メンター制度を作る: 新入社員が先輩社員と会い、キャリアアップや学習のチャンスについて相談できる機会を設けます。
- コーチングを提供する: コーチを招き、従業員のスキルを評価して、スキル開発につなげます。
- トレーニングプログラムに投資する: 従業員が興味のある分野でスキルアップできるよう、定期開催のトレーニングプログラムを実施します。
トレーニングやキャリア開発の機会を提供すると、従業員に投資しようとする会社の姿勢を示すことになります。これによって従業員の離職率が下がるだけでなく、チームのスキルを高めることもできるので一石二鳥です。
6. 高い条件を提示する
どこよりも素晴らしい職場で、企業文化にも責任者にも非の打ち所が無い企業であっても、報酬が公平に与えられていなければ、離職率へのダメージを防げません。競争力のある報酬と包括的な福利厚生を整えることが、離職率を下げる最も効果的な方法です。
目指すべき競争力のある条件には、以下のような内容が含まれます。
- リモートワークの機会: 在宅勤務や、在宅とオフィスのハイブリッド形式を選択できると、応募者が増え、従業員の満足度も高まります。
- 健康・ウェルネス・保険: 心身の健康を守る保険やプログラムで、従業員の安全を守ります。
- 柔軟な勤務体制: 最近は柔軟な勤務時間を採用する企業が増えており、各自のニーズに合わせて従業員が働きやすい時間に勤務できるようにしています。
- 週4日勤務: 週4日勤務に切り替えることで、長くなった休みの日に従業員がリラックスする時間が増えます。この方法では、生産性を維持しつつ(多くの場合、生産性を上げながら)、仕事の満足度を高めることができます。
- 休暇日数: 従業員の休暇日数は、会社の所在地(国)によって異なります。日数を増やすと、従業員の信頼を獲得しやすくなります。
- ロイヤリティポリシー: ボーナスや定休日の追加、目標達成や再雇用の柔軟性などによっても、離職率を抑えられます。
離職率が極めて低い企業では、上記のような追加条件だけでなく、ほかにも多くの特典を提供していることが珍しくありません。離職率の削減と同時に従業員体験の改善に取り組み、一流の人材を獲得して維持しましょう。
離職率に関するFAQ
- 自発的離職率と非自発的離職率の違いは何ですか。
- 良い離職率はどのように判断できますか。
- 離職率を改善するにはどうすればよいですか。
SurveyMonkeyで従業員の満足度を調査し、離職率を減らしましょう
企業の離職率を把握するには、離職率を定期的に計算して監視する必要があります。高い離職率は、従業員体験の問題を知らせる徴候です。
離職率対策を打つことにより、従業員体験を改善し、価値提案を強化できます。SurveyMonkeyを使って、従業員エンゲージメントを追跡・改善する方法をご覧ください。
その他のリソースを見る

人事リーダー
人事リーダー向けのこのツールキットは、比類なき従業員体験の構築をサポートします。

フィードバックで組織の透明性を高め、信頼関係を築く
全関係者に正確な関連情報を提供し、組織の透明性を実現しましょう。

woomが従業員と顧客の体験を改善した方法をご覧ください
woomがSurveyMonkeyで大規模な多言語アンケートを実施して、従業員の体験を改善し、顧客からの洞察を獲得した方法をご覧ください。
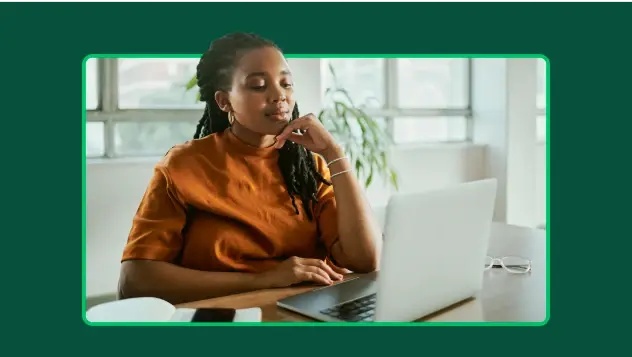
今日の労働環境を理解して再構築するための職場のトレンド3選
職場のトレンド、ワークライフバランス、自宅勤務、リモートワークと出社勤務の違いに関する新たな調査